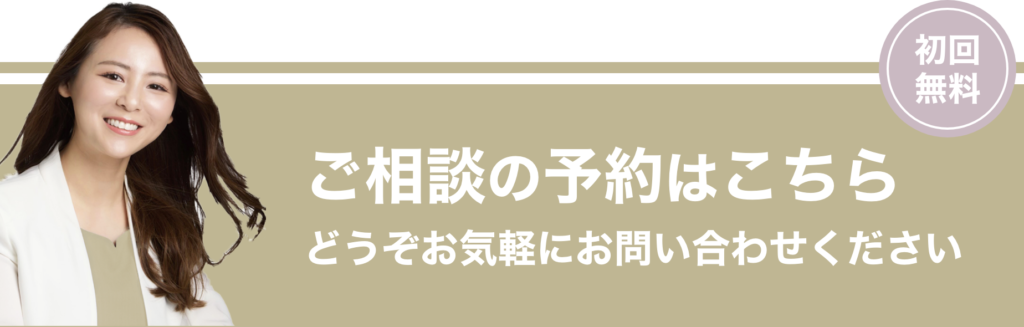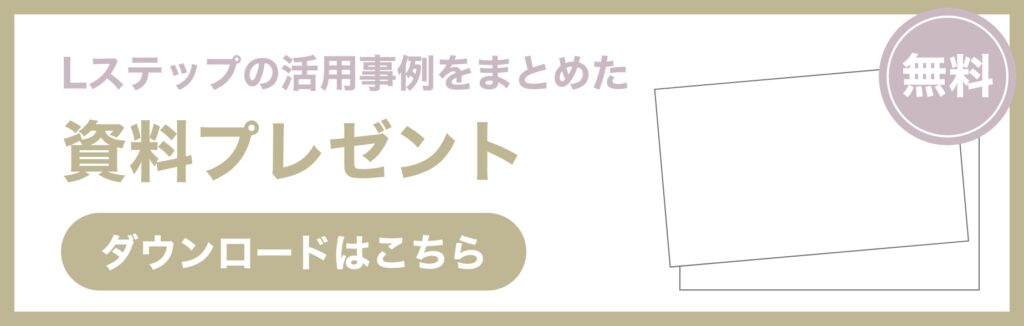近年、「事業へのIT導入」が急速に進んでいますよね。
今までアナログで処理していたものを、ついにデジタル化することを検討している…という中小企業・小規模事業者さんは多いのではないでしょうか。
今回の記事では、これから事業にITツールを導入しようと考えている事業者さんに絶対知っておいてほしい「IT導入補助金」について、
・事業の概要や補助金の種類
・2023年度の補助金予想
・IT導入補助金を利用するまでの流れ
・利用における注意点
などについて、詳しくご紹介していこうと思います。
当社はLステップ及びLINE公式アカウントの活用を中心に、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援している会社です。
前年度に引き続き2023年3月6日に「2023年度IT導入支援事業者」として採択されました。
2023年度のIT導入補助金を利用したLステップ交付申請に向けた申請サポートも開始しておりますので、補助金利用を検討しておられます際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
目次
IT導入補助金とは
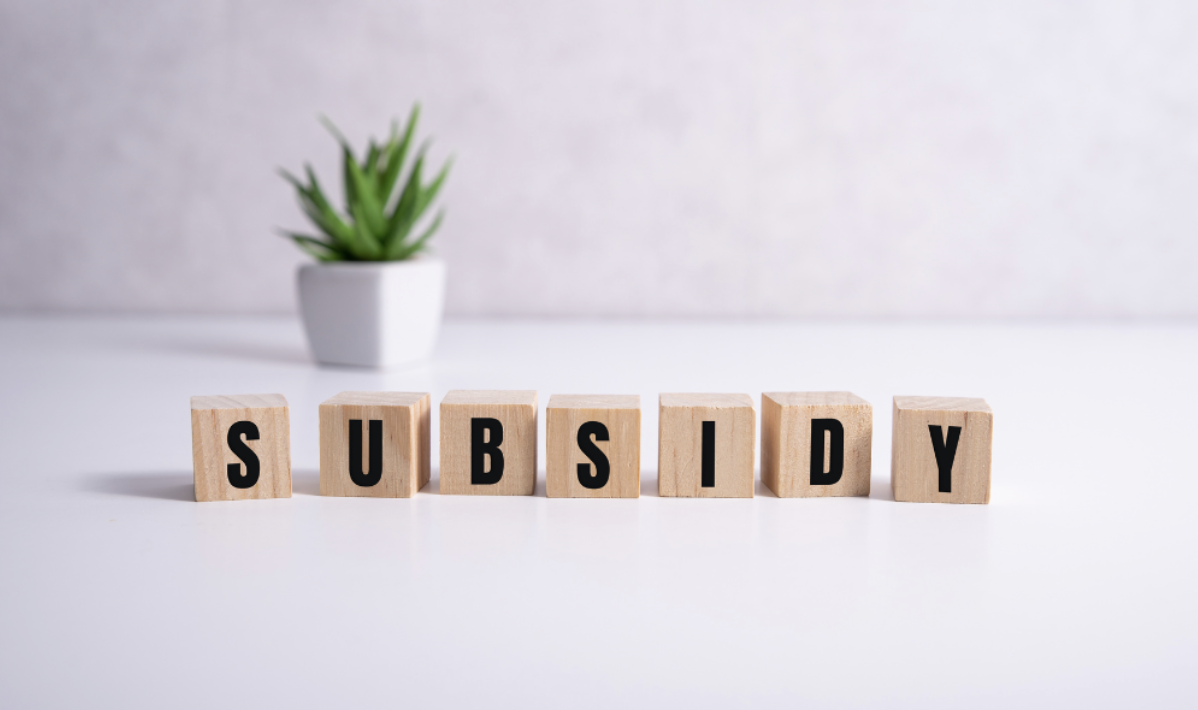
IT導入補助金とは、その名の通り「これから事業にITツールを導入する中小企業・小規模事業者さんに向けての、その導入費用の一部を補助してもらえる制度です。
これらの点が目的として挙げられているため、助成金を受け取ってITツールを導入した結果、事業にどのような好影響があったかを評価・報告するまでが一連の流れとなっています。
IT導入補助金の種類

IT導入補助金の種類は、ざっくりと大きく3つに分けることができます。
通常枠(A・B類型)
通常枠はA・B類型に分かれており、
・自社の現状・環境から事業の強み・弱みを分析する
・分析結果をもとに、経営課題に合ったツールを導入して事業の効率化・成長を狙う
この目的のもと利用できる補助金。導入したツールの1/2額の補助が受けられます。
A・Bの違いは「補助金申請額」にあり、A類型は “ 30万円以上150万円未満 “ 、B類型は ” 150万円以上450万円以内 ” となっています。(2022年度の情報。2023年度は後述の通り金額の枠が変更となる可能性があります)
LINE公式アカウントやLステップなどはこの項目の「A類型」に分類されます。
2022年度のA類型は1/2補助30万円以上~、つまり60万円以上のツール導入が必要だったためハードルが非常に高く利用がしづらかったのですが、2023年度は採点申請額が下がると公表されたので、申請しやすくなることが予想されています。
【2023年4月 最新情報!】採点申請額の引き下げの詳細が公開されました。
・通常枠A類型…補助金額5万円〜150万円(下限引き下げ)
・補助対象経費…ソフトウェア購入費・クラウド利用料最大2年分(期間を長期化)
より小規模なツールでも補助対象となるので、しっかりと活用していきましょう!
セキュリティ対策推進枠
セキュリティ関連のツールを導入する際に受けられる補助金の枠で、サイバーインシデント・サイバー攻撃の被害から事業を守ることが目的とされています。
・サービス利用料の1/2以内・最大100万円
・最大2年分の利用料補助
などの条件が定められています。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトなどが対象。
インボイス取引対応も見据えた企業間のデジタル化を推進するための枠となります。
【予測】2023年度、IT導入補助金はもらえる?

2023年3月、「IT導入補助金2023」の詳細が発表されました。
今年度もIT導入補助金を活用したツール導入が可能です!
ここでは、LINE公式アカウント・Lステップの補助分類とされている「通常枠(A・B類型)」のスケジュールを掲載していきます。
【2023年度通常枠・1次締切分】
- 締切日:2023年4月25日(火)17:00(予定)
- 交付決定日:2023年5月31日(水)17:00(予定)
- 事業実施期間:交付決定~2023年11月30日(木)17:00
- 事業実績報告期:2023年11月30日(木)17:00
【2023年度通常枠・2次締切分】
- 締切日;2023年6月2日(金)17:00(予定)
- 交付決定日:2023年7月11日(火)17:00(予定)
- 事業実施期間:交付決定~2023年11月30日(木)17:00
- 事業実績報告期限:2023年11月30日(木)17:00
締切日はあくまで予定となっていますが、期限内に申請できるように早めに準備を進めておく必要があります。
IT導入補助金の利用の流れ

IT導入補助金の利用の流れは、複数のステップに分かれています。
手順が多いためやや複雑に感じるかもしれませんが、ツール構築の支援事業者に相談しながら進めれば問題ありません。
早速、補助金利用の手順全体像を確認していきましょう。
①GビズIDの取得
GビズIDは、簡単に言うと「行政サービスへのログイン・手続きを楽にする」というアカウントのことです。
今回はIT導入補助金の申請に利用しますが、他にもさまざまな行政サービスへのログイン・申請手続きなどをすることができます。
すでに有効なGビズIDプライムアカウントをお持ちの方はそのままお使い頂けます。
>> GビズIDの作成・取得はこちら
②どのITツールを導入するかを決める
現状の事業の課題・方向性を洗い出し、どのツールを導入するのが効果的なのかを検討・決定しましょう。
迷われる方が特に多いのが「LINE公式アカウントとLステップ、どちらを導入すべきか?」という疑問。
当社ではこのようなご相談も受け付けておりますので、迷われている方はお気軽にお問合せください。
③公募スケジュールの確認
次に、公募スケジュールの確認を行います。
2023年度の普通枠のスケジュールは、上に掲載した通り1次締切分が4月25日・2次締切分が6月2日予定。
しかし予算が上限に達した場合、早期終了となる可能性もないわけではありません。
とくに今年からはIT導入補助金の利用ハードルが一部下がっているため、応募が多くなることが予想されます。余裕を持った行動が大切かもしれません。
交付決定日、事業実施期間、事業実績報告期限の日程もしっかりと把握し、年間の予定ややるべき事項をまとめておくと分かりやすいでしょう。
④支援事業者を選定し、連絡を取る
IT支援事業者とは、補助事業を実施するうえでの共同事業者(=パートナー)のことを指します。
ツールの構築はもちろんのこと、中小企業・小規模事業者等のみなさまの生産性向上のためにツール導入・経営診断ツールを利用した事業計画の策定の支援、各種申請等の手続きなどのトータルサポートを行います。
なお、IT導入支援事業者が事務局に登録し、認定を受けたITツールのみが、IT導入補助金の補助対象となりますので、ご注意ください。
当社ではLINE公式アカウント・Lステップ・ECサイトの構築などが対象となります。
⑤交付申請手続をし、交付決定を受ける
④で支援事業者と連絡を取ったら、ツールの提案や仮選択などの事前準備を進めたのちに補助金の交付申請を行います。
この部分も支援事業者からのサポートを受けられますので、ご安心ください。
交付申請後に申請が採択されると「交付決定」の連絡が届きます。
なお、この交付決定が届く前に発注・契約・支払いなどを行った場合は補助金の対象外となってしまいますので、十分注意するようにしてください。
⑥支援事業者からツール納品・支払い
交付決定通知が届いたのちに、支援事業者よりツールの納品を受け支払いを済ませます。
必要時ツール導入のサポートなども受けることが可能です。
⑦事業実績報告・補助金の交付
事業実績報告は、交付決定を受けた申請内容に基づきITツールの導入が完了しているか確認するものです。
こちらを提出したのち、補助金の交付が行われることとなります。
⑧事業実施効果を報告(補助金交付から3年間必要)
IT導入補助金を利用した場合、補助金交付から3年間「事業実施効果」を提出する必要があります。
このツールを導入してから、事業にどんな影響があったか・効率や生産性はどのくらい上がったのかなどを報告する書類になりますので、忘れずに提出する必要があります。
IT導入補助金を利用する際の注意点
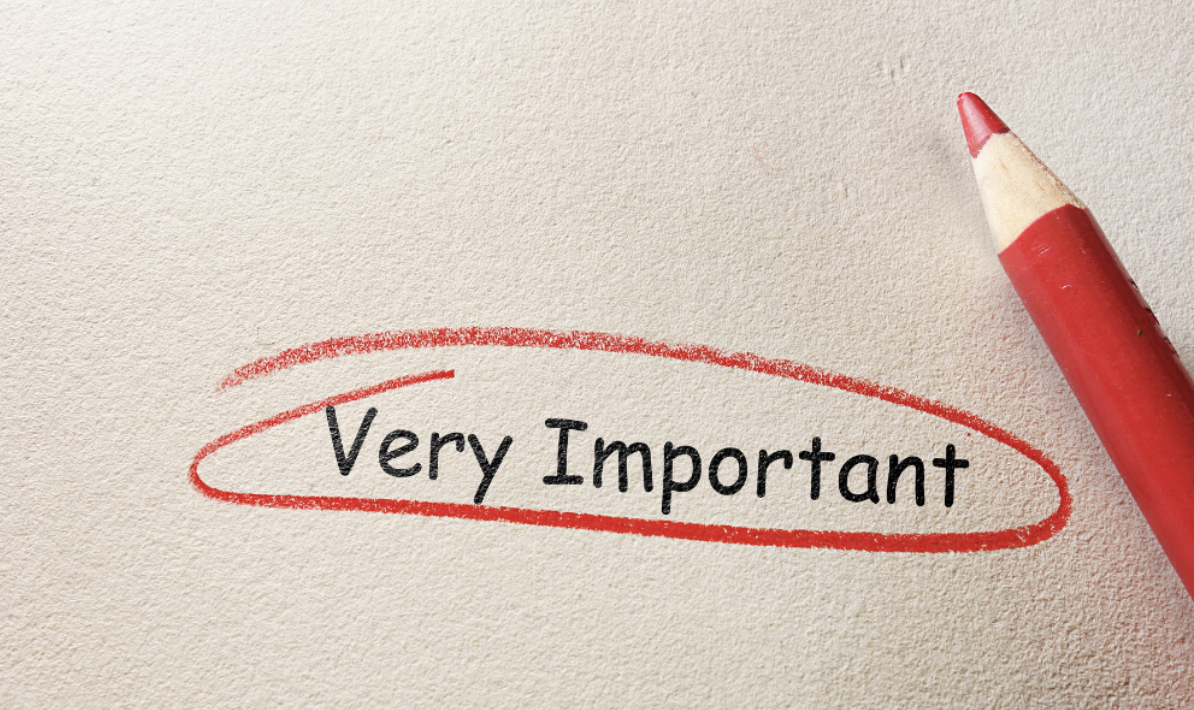
IT導入補助金は、申請・利用において3つの注意点が存在します。
補助金交付までに時間がかかる
IT導入補助金は、申請してすぐ貰えるわけではありません。
補助金交付のタイミングはツールの支払いをした後になりますので、諸費用はしっかりと全額準備しておく必要があります。
申請後必ず採択されるとは限らないためタイムロスが発生する
「申請=必ず採択される」というものでもありません。
【2022年度の採択実績】
・通常枠 55.9%
・デジタル化基盤導入枠 85.5%
・平均採択率 66.4%
半分以上が採択されているものの、採択されなかった時に再申請する場合のタイムロスが発生する可能性もあることを知っておきましょう。
【法人の場合】1回以上決算を終えている必要がある
こちらは法人の場合に限りますが、申請要件として「1回以上の決算を終えていること」が入っています。
まだ決算が終わっていない状態であれば、来年度以降の利用を検討すると良いでしょう。
申請後、採択されやすくなるコツはある?

ITツールは大きなお金を出して購入するものなので、「平均採択率が66.4」という数字を見ると本当に補助を受けられるか不安になる方もいらっしゃると思います。
実は採択されやすくなるコツは色々あるのですが「ITツールを制作してくれる支援事業者に相談する」のが安心です。
今まで何社ものIT導入補助金申請→採択に関わってきた当社でも、LINE公式アカウント・Lステップなどの作成・ご相談に乗ることが可能です。
補助金について少しでもご不安がある場合は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください!
まとめ:IT導入補助金公募は2023年も公開される可能性が高い

【2023年4月 最新情報!】
採点申請額の引き下げの詳細が公開されました。
・通常枠A類型…補助金額5万円〜150万円(下限引き下げ)
・補助対象経費…ソフトウェア購入費・クラウド利用料最大2年分(期間を長期化)
今回の記事で解説した通り、2023年もIT導入補助金の公募が開始されることが決定しました。
通常枠の公募締め切りは4月25日(火)17:00・6月2日(金)17:00(どちらも予定)となっていますので、時間に余裕がない方もいるかもしれません。
当社はLステップ及びLINE公式アカウントの活用を中心に、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援している会社です。
前年度に引き続き2023年3月6日に「2023年度IT導入支援事業者」として採択されました。
IT導入補助金の利用を検討しているけれど、何から取り掛かるべきか分からない…という中小企業・個人事業主さんがいらっしゃれば、IT導入補助金2023の支援事業者である当社にお気軽にご相談ください。
より小規模なツールでも補助対象となるので、しっかりと活用していきましょう!